イラストレ−タ−柴田賢二さんの作品
1959年マン島TTレースにRC142により初出場を果たしたホンダ・チームは、谷口尚巳が6位に入賞し、さらに“メーカーチーム賞”を獲得するというまずまずの結果を残した。しかし、同時に、車体の剛性不足による操安性の問題やブレーキ性能が劣っているといったマシンの問題点も露呈し、帰国直後から翌年に向けての開発が進められたのだった。その結果、1960年の世界グランプリには、オーソドックスなテレスコピック・フォークを持つRC143が投入された。従来の直立シリンダーを35°前傾させたエンジンの出力もRC142が17.4ps/14,000rpmであったのに対して23ps/14,000rpmまでアップしたのである。2年目の1960年にホンダ・チームは、マン島TTレースだけではなく、計6戦の世界グランプリに参戦し、125ccと250ccの両クラスに出場した。
RC143に乗るライダーでは、ジム・レッドマンがダッチTT(オランダGP)とイタリアGPの2戦で4位に入賞し、マシンの性能が表彰台獲得まであと一歩のところに近づいていることを証明した。翌年、世界グランプリ開幕戦スペインGPの125ccクラスに、新型モデルの開発の遅れのため前年に引き続き投入されたRC143はトム・フィリスのライディングにより優勝。ホンダにとっての世界選手権初勝利ともなる記念すべきモデルとなった。
世界選手権ロードレース125ccに挑戦して2年目、'61年第1戦スペインGPで、ホンダがグランプリレース初優勝を飾ったマシン。(優勝車 No.60
T.フィリス)
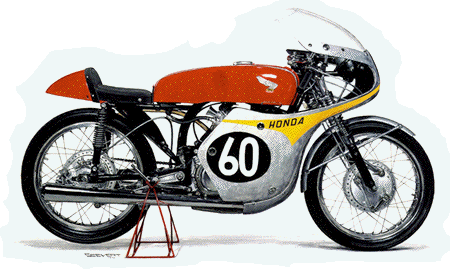
1960 HONDA RC143
| エンジン種類 | 空冷4サイクル並列2気筒DOHC4バルブギヤ駆動 |
| 排気量 | 124.68cm3 |
| 最高出力 | over 23PS/14,000rpm |
| 最高速度 | over 180km/h |
| 車両重量 | 93kg |
| 変速機 | 6段変速 |
| サスペンション(前) | テレスコピック |
| サスペンション(後) | スイングアーム |
1960 / ホンダ RC143
●RC143/主要諸元
全長×全幅×全高 1,874×650×930mm ホイールベース 1,265mm 乾燥重量 93kg エンジン形式 空冷2気筒 カム形式/駆動 DOHCベベルギヤ バルブ数 4 総排気量 124.62cc ボア×ストローク 44×41mm 最高出力 23ps/14,000rpm キャブレター形式 ピストンバルブ 点火方式 マグネトー 変速機 6段 潤滑方式 ウェットサンプ圧送併用 フレーム形式 バックボーン 前ブレーキ ツインパネルシングルカムドラム 後ブレーキ形式 シングルパネルツインカムドラム 前サスペンション形式 テレスコピック 後サスペンション形式 スイングアーム 前ホイール形式 H型アルミリム/スポーク 後ホイール形式 H型アルミリム/スポーク 前タイヤサイズ 2.50-18 後タイヤサイズ 2.75-18
1959型RC142を発展させた1959年型125ccクラスマシン。エンジンは35度前傾させた全くの新設計。フレームやサスペンションも当然新型となり、スマートなカウルに包まれまったく新しいマシンに生まれ変わっている。最高出力もRC142の18ps/13,000rpmから23ps/14,000rpmに向上しており、操縦性を含めた総合的な戦闘力は格段に向上している。このRC143からタンクがホンダレッドに塗られ、以後一貫して用いられたRCカラーリングがスタートしている。
| ●排気量:124.62cc ●気筒数:空冷2気筒直立 ●ボア×ストローク:44×41mm ●圧縮比:10.5 ●最高出力:23ps/14,000rpm ●最高速度:180km/h以上 ●前タイヤ:2.50-18 ●後タイヤ:2.75-18 ●乾燥重量:93kg |
RC143
1960年(昭和35年)
1960年(昭和35年)
